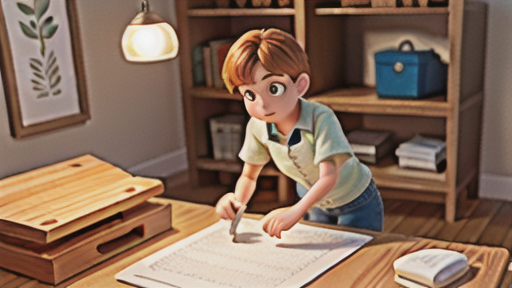陶芸家になるには

しごとガイド
陶芸家とは、陶磁器を作る職人さんのことです。

しごと選び中
陶磁器って、どんなものですか?

しごとガイド
食器や衛生陶器、タイル、碍子など、私たちの日常生活に欠かせないものが挙げられます。

しごと選び中
なるほど、陶芸家は、そういったものを手作りしているんですね。
陶芸家とは。
* 陶芸家とは、粘土を原料として、高温で焼成して作られる陶磁器の製造や制作を行う職人のことです。
* 陶磁器は、私たちの日常生活に欠かせない食器やタイル、衛生陶器、碍子などを含む、粘土を原料として高温で焼成して作られる製品のことです。
* 陶磁器製造では、伝統的な手作業による製造法から、コンピュータやロボットを使った最先端の製造法まで、さまざまな製造方法が用いられています。
* 日本には、愛知県の瀬戸市、常滑市、岐阜県の多治見市、土岐市、三重県の四日市市、滋賀県の信楽市、石川県の小松市、佐賀県の有田町、栃木県の益子町、岡山県の備前市、山口県の萩市、愛媛県の砥部町など、陶磁器の産地として知られる地域がたくさんあります。
陶芸家へのキャリアパスは、
-陶芸家のキャリアパス-
* 陶芸家になるには、特に学歴や資格は必要ありません。
* 陶芸の仕事に就くには、求人募集や縁故を通じて事業所に就職するのが一般的です。
* 事業所では、現場で作業を通じて仕事のやり方を覚え、技術や技能を習得します。
* 現在では、成形や絵付けでアート的なセンスが求められるようになってきており、できれば工業高校などで技術やデザインを習得されることを勧めます。
* 手作業による工芸的生産では、一人前になるには少なくとも3~5年の修行が必要だと言われています。
* 公共職業訓練校や窯業大学校などで高度な技能を習得することも可能です。
陶磁器製造の工程

-陶磁器製造の工程-
陶磁器製造の工程は、大きく分けて以下の5つの段階に分けることができます。
1. 原料の調合
2. 成形
3. 乾燥
4. 素焼き
5. 施釉・本焼き
-1. 原料の調合-
陶磁器の原料は、粘土、長石、石英の3種類です。粘土は、陶磁器の主成分であり、塑性と粘着性があります。長石は、陶磁器に強度と白さを与えます。石英は、陶磁器に硬さと耐熱性を与えます。
3種類の原料を一定の割合で混ぜ合わせ、水を加えて練り上げます。練り上げた原料は、しばらく寝かせてから成形します。
-2. 成形-
成形は、轆轤(ろくろ)や手びねりなど、さまざまな方法で行うことができます。轆轤は、回転する円盤の上に粘土を置き、手で形を整える方法です。手びねりは、粘土を直接手で成形する方法です。
成形した陶磁器は、乾燥させるためにしばらく放置します。
-3. 乾燥-
乾燥は、自然乾燥と人工乾燥の2つの方法があります。自然乾燥は、陶磁器を風通しの良い場所に置いて乾燥させる方法です。人工乾燥は、乾燥機を使って陶磁器を乾燥させる方法です。
乾燥させた陶磁器は、素焼きを行います。
-4. 素焼き-
素焼きは、陶磁器を窯に入れて焼成する最初の工程です。素焼きの温度は、約1,000℃です。素焼きを行うことで、陶磁器に強度がつき、施釉の準備が整います。
-5. 施釉・本焼き-
施釉は、素焼きした陶磁器に釉薬を塗る工程です。釉薬は、陶磁器に光沢と防水性を与えるものです。釉薬を塗った陶磁器は、再び窯に入れて焼成します。本焼きの温度は、約1,200℃~1,300℃です。
本焼きを終えた陶磁器は、完成です。
陶磁器製造の産地

-陶磁器製造の産地-
陶磁器は、粘土を成形して焼いて作った器です。その歴史は古く、紀元前6000年頃には、現在のイランやイラクで陶磁器が作られていたという記録があります。その後、陶磁器製造の技術は世界各地に伝わり、さまざまな地域で独自の陶磁器が作られるようになりました。
日本でも、古くから陶磁器が作られており、全国各地に陶磁器製造の産地があります。その中でも、特に有名な産地をいくつかご紹介します。
-瀬戸-
瀬戸は、愛知県瀬戸市にある陶磁器の産地です。瀬戸焼は、平安時代後期に始まったとされ、その歴史は1000年以上になります。瀬戸焼の特徴は、黄色の土を使用していることで、素朴で温かみのある風合いが特徴です。
-美濃-
美濃は、岐阜県土岐市にある陶磁器の産地です。美濃焼は、鎌倉時代初期に始まったとされ、その歴史は800年以上になります。美濃焼は、多様な種類の陶磁器が作られており、日常使いの食器から工芸品まで、さまざまなものが生産されています。
-有田-
有田は、佐賀県有田町にある陶磁器の産地です。有田焼は、17世紀初め頃に始まったとされ、その歴史は400年以上になります。有田焼は、白磁や色絵磁器が有名で、その美しさから「日本の陶磁器の最高峰」とも言われています。
-九谷-
九谷は、石川県加賀市にある陶磁器の産地です。九谷焼は、17世紀半ば頃に始まったとされ、その歴史は300年以上になります。九谷焼は、五彩手と呼ばれる五色の絵付けが特徴で、華やかで美しい作風が特徴です。
-信楽-
信楽は、滋賀県甲賀市にある陶磁器の産地です。信楽焼は、平安時代末期に始まったとされ、その歴史は800年以上になります。信楽焼の特徴は、狸の置物です。信楽焼の狸は、縁起物として知られており、全国各地で親しまれています。
陶芸家の仕事内容

– 陶芸家の仕事内容
陶芸家は、粘土や陶土などの素材を使って、器やオブジェなどを作る芸術家です。
陶芸家になるためには、専門の学校や大学で陶芸を学んだり、陶芸工房で修業を積んだりする必要があります。
陶芸家の仕事内容は、大きく分けて以下の4つです。
1. 粘土や陶土の調合
2. 器やオブジェの形や大きさの決定
3. 器やオブジェの制作
4. 器やオブジェを窯で焼成
陶芸家は、まず粘土や陶土を調合して、自分の作品に合った素材を作ります。
次に、器やオブジェの形や大きさを決定し、それを基に粘土や陶土を成形していきます。
成形した粘土や陶土は、窯で焼成します。
焼成温度や時間は、作品によって異なります。
焼成が終わると、作品は完成します。
陶芸家は、作品を作るだけでなく、作品を展示したり、販売したりする必要があります。
また、作品の制作過程を記録したり、作品に関する論文や記事を書いたりすることもあります。
陶芸家は、芸術家として活躍できる喜びを感じながら、作品を通して人々に感動を与えたり、美意識を伝えたりすることができるやりがいのある仕事です。